昔から短気な性格で、かつ他人に対してせっかちであり、「待つ」ことが下手だった。その価値観が最初に覆されたのは、若い頃急性腎炎で入院した時の事だ。外科的な疾病もそうだが、特に不随意な、自分の意思では如何ともしがたい内臓疾患の病気のたぐいの快癒には、自然の治癒力が必要である。何と言うか「ボーっとして待つ」ことが良いのだそうだ。不随意な神経や仕組みを司るのは、意識下の力を総動員する必要があり、それには、自分の神経がピリピリしていては駄目で、ゆったりとしていると、不思議と思わぬ力が集まってくるという。様々な心配事や自分にとっての問題を、それはそれとして自分の前に幾つか雲の様に浮かべて置いて、環境を変えボーっとしていると、突然思わぬ良いアイデアに遭遇する事は誰しも少なからず経験していると思うが、やる事をやった後は「待つ」ことが肝要なのである。
私共のエクゼクティブ・サーチの仕事は、典型的な「待つ」仕事のジャンルである。あるタイミングで良いご縁を取り持つ訳だが、クライアントの意思決定、候補者の決断を含め、なかなか私共の思い通りにはならないことは勿論、徹底的に「待つ」姿勢が要求される。熟練者になると、「仕掛けながら待つ」という高等技術を使いこなすコンサルタントもいる様だが、自分は無骨なのでやはり待ちに待つのである。以前の会社では、仕掛けて実績を挙げることに慣れていたため、この仕事に移ってから数年して、「ああ、これは待つビジネスなのだ」という事に気付いた。自分から仕掛けてゆく事は限られ、顧客や候補者の決断を待つというビジネスに移ったことが、かなり特殊なジャンルの業界に入ってしまったという感が強かった。
しかし、世の中の大切な事のほとんどは、「待つ」ことなのではないか・・・という事に最近気付き始めている。遅ればせながら、大変お恥ずかしいのだが・・・。作物を育てる、人を育てる。生命の誕生と終始。人との信頼関係。病気の治癒。恋愛の成就、愛憎の収拾。などなど、世の中の多くの重要な局面には、必ず「辛抱強く見守る」という要素が入っている。自分から仕掛けるよりも、ほがらかに待ってその時の熟成を待つ・・・と言う姿勢である。こういう事は、実は人生の隆盛期や円熟期、いわゆる器量、体力、気力、経済力の上昇期や円熟期には、なかなか気付きにくい事ではないだろうか?あるピークが過ぎて「壮年期」になって来ると不思議に見えてくるものがあるのである。
我々のビジネスでは、待ちに待って、こちらの期待する方向に物事が動かないことの方が多い。人の人生に関する事である。当たり前ではないか。ただ、この様な経験を繰り返し積み重ねると、自分自身の人格形成にも何らかの足しになる様な気がする。負け惜しみではなく、そう思うのである。各人の人生の転機の様々な「課題に向き合い、寄り添う」という凝縮した経験を飽きずに繰り返していると、疑似的ではあるが何回かの人生を生きた様な錯覚に陥ることがある。それ自体良くもあり悪くもある経験ではあるが、それぞれ「人には事情がある」のだなあ・・・ということ、「世の中はなかなか思い通りにはゆかないこと」が、腹に落ちる。ある面では思い通りにいっても、その裏側ではその大きな代償があったり、不運の連続の様な方が、その裏では掛け替えの無い美点を身に着けたりする。表現が難しいが、「積極的な諦観」という様なものが身に付く。喜びに有頂天になり過ぎず、悲しみにしょげ過ぎもしないという姿勢である。悟りきったことを言う主旨では全くないが、「待つ」という我々のビジネスの奥は意外に深く、15年経っても飽きることが無い。
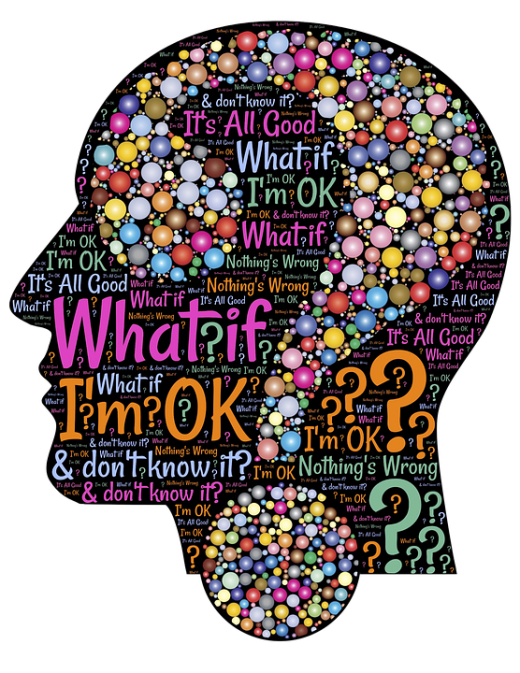
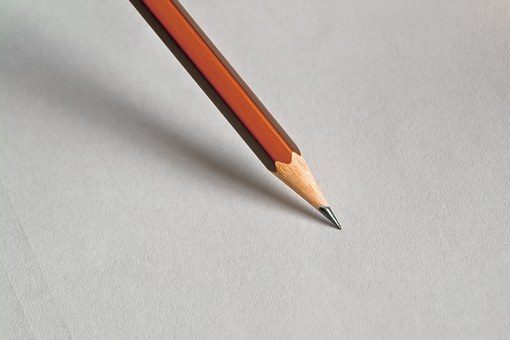
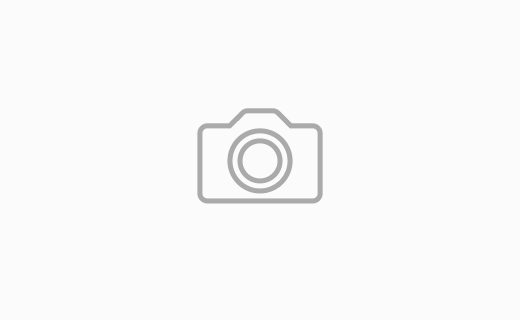
最近のコメント