一週間前に4年ぶりのチェアマンの投票があり、久々スタントンチェイスのグローバルミーティングに参加した。今回の開催場所はコペンハーゲン。北欧の港町で10時間のダイレクトフライトである。晩秋色濃く人々はコートと手袋を手にしていた。シンガポール支店の責任者とホテルに着くなり、町のカフェで軽い夕食をとり、親交を温める。ニシンで有名な町だが、ニシンの酢漬け料理、リブのステーキ、サラダというメニューだ。Skypeでは頻繁に議論している相手だが、3年程前に弊社にジョインし、会うのは初めてである。4泊6日のグローバルミーティングの中で、売上の三分の二を海外ビジネスで稼ぎだしている彼の辣腕ぶりをつぶさに見る事になる。
シンガポール人だが、苦労人らしく起業家精神に溢れていて、ケタケタと甲高い声が少し煩いが、気さくで明るい好人物である。ネットワーキングとは一部日本語にもなっているが、全世界45か国70オフィスから120名以上が集まる外人中心の集団の中でのネットワーキングは日本人の感覚とは少しニュアンスが異なっている。各オフィスの責任者が信頼できるローカルオフィスの個人に対し、自分のクライアントからの信頼を担保に案件を紹介したり、(これをExport)紹介されたり(これをImport)するのである。言語力は勿論だが、人種や宗教、政治や文化を超えて、「信頼できる友達」になるスキルが要求される。言うのは容易いのだが、これがなかなか一筋縄では行かない。彼は持前の気さくな明るさと無国籍な感覚をベースに、各国の責任者の間を縦横無尽に飛び回り、時にはおどけ、時には真顔で、自分の国の状況や相手の国の状況を詳細に聞き取ってゆくのである。
まず第一に驚くのは、相手の名前を覚える素早さである。外人にはある程度共通している技能であるが、彼の記憶力には舌を巻く。何故なら、相手国の責任者と案件毎のコンサルタント名と関連するクライアント責任者を二~三名、それに関連する候補者を数名というセットが、付き合いのあるローカルオフィス数十件に拡散するのである。私には到底、我慢がならない記憶量である。今回の4日間でのパーティや会議の席上で、知り合いを見つけ、それぞれの案件毎の話を展開する訳である。また常に新しいコンサルタントが各国から参加してくるので、顔、名前、国籍、オフィスを一致させてゆかねばならない。各人名札をつけているとは言え、最終日に「あれっ、誰だったっけ?」というのは基本、許されない。
第二に、言語力だが、ユーモアを含め軽快にあるスピード感でネットワーキングしてゆく力は、独特のものである。英語力自体は、複雑なコンセプトを頭で事前に構成しなくともリアルタイムに話始め、辻褄を合わせる力が必要であり、いざとなれば論理武装して冷静に議論する力を併せ持つ。更に、どうしても追いつけないのが、「デモクラシー」に対する感覚である。日本以外のローカル国はデモクラシーを汗と涙と血を流しながら獲得して来ているのだが、日本人のそれは幸か不幸か全く異なる。何がFairで何がNot Fairか?という歴史観や識別眼が基本的に異なるので、複雑で利害の反する議論になると、冷静に議論を深めてゆく必要があるのだが、(でないと殺し合いになる事を承知しているので・・・)我々日本人の大半はそれを苦手としている。甘えがあるのである。
その中で、最終日には4年ぶりのチェアマンの改選があり、二人の候補者のプレゼン後の決選投票となった。二人のプレゼンを聞き、その後Q&Aを皆から受けるのである。一人の候補者のプレゼン時に対抗者は部屋の外に出される。米国人とアラブ人の決戦であった。このプレゼンも何がFairであり、何を正当に守るものとして、これからのスタントンチェイスをリードするのか?が問われるのである。その後、我々ローカルの責任者からの投票が行われ75%マジョリティーで米国人が選出されたのだが、今回の彼のプレゼンスピーチは、内容、態度、Fairさ、チェアマンとしての覚悟、どれを取っても秀逸なものだった。特に、Q&Aのセッションでは通常かなり意地悪な質問もされるのが普通なのだが、二人の質問者からは、彼の長年のHands OnでSpeedyで丁寧な対応に対する賛辞が送られ、「貴方の様な方をチェアマンに迎える事が出来れば、それは我々の誇りである。」という意味の言葉を掛けられた時、なんとその候補者はその場に立ち尽くし、男泣きをしたものである。それを受けて、皆がStanding Ovationを送った。論理性やFairness、礼儀正しさ、品格、冷静さを問われるその場にあって、何故か違和感は無く感動的な場面だった。
この様な、起業家精神に富むパートナーシップで組織を運営し来年で25周年を迎える。ローカルの主体性を重んじ、自分の事で責任を果たすのは当たり前、他人の為に何が出来るか?というビジョナリーな形態で、よくも四半世紀も続いたものである。私も16年間在籍しており日本のプレゼンスはそれなりにあるのだが、まだまだネットワーキングが十分とは言えず、良く知ってもらう為に、プレゼンを行って来た。我々のオフィスも今後10年を見据え、新たなスタートを切る必要性を再確認し、帰国の途に着いた。




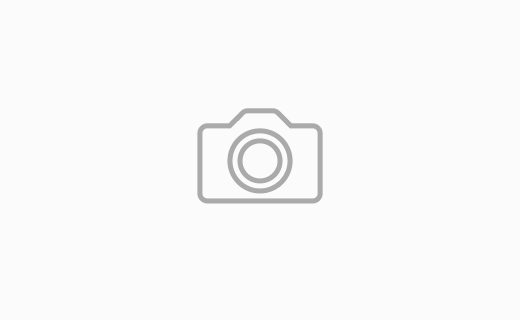
最近のコメント